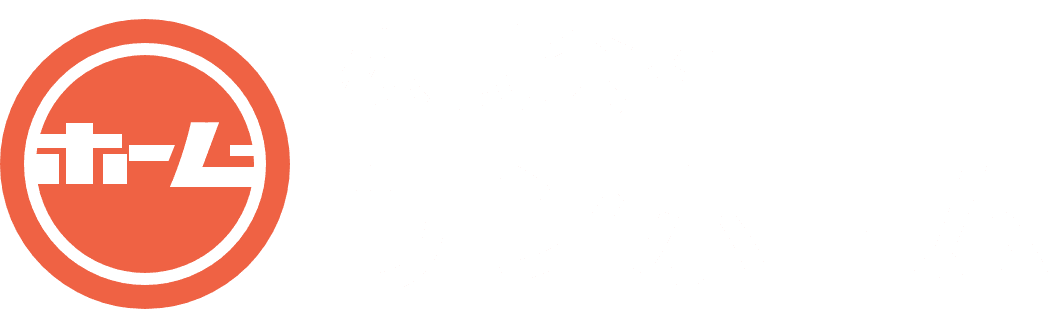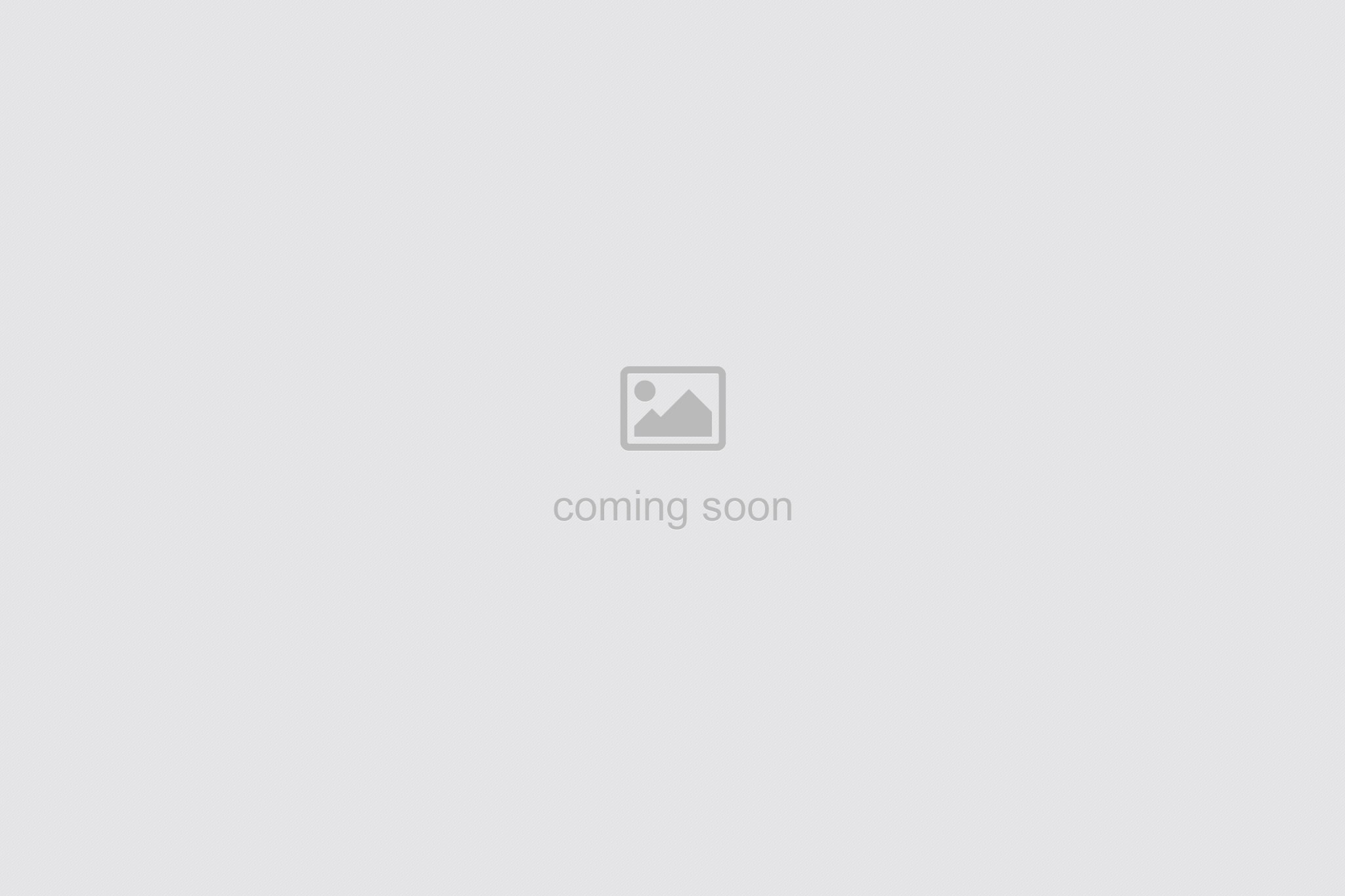ブログ
『高齢者問題』と『成年後見人』と不動産売却(その2)
2023-03-08
カテゴリ:不動産(住宅)売却,その他
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【『高齢者問題』と『成年後見人』と不動産売却】(その2)について
ご自宅は本人の生活の拠点ですので、居住用は非居住用と異なり家庭裁判所の許可が必要となります。※非居住用に比べて時間もお金もかかります。
また成年後見人制度の目的が本人保護に配慮していますから、
1、売却の必要性 2、本人の生活や看護の状況、本人の意向確認 3、売却条件 4、売却後の代金の保管 5,親族の処分に対する態度等が許可の成否に対する判断材料となります。
生活費や看護費の調達目的での売却ならば1番の要件は満たしますが、必ずしもそういう場合だけではありません。
例えば、子供が県外在住で定期的に様子を見にいけない等高齢者が独居生活をする上での防犯上の必要性から介護施設・医療機関への入院を促し、その結果として『母親あるいは父親は認知の症状が有り、一人で生活することは困難なので処分したい』と子供が不動産屋に依頼される場合もあります。むしろこのケースの方が多いように感じます。
つい先日も、施設入居後に高齢者本人が『自宅に帰る』といって聞かなかったという話もあります。 その場合は3番の『本人の意向』の要件が満たされないので家庭裁判所の判断に委ねられ、どういう判断になるか私にはわかりませんが、成年後見人制度の本人保護の目的から逸脱するようにも感じます。
一方、成年後見人制度活用後の高齢者の預貯金の引き出しに際しては、その都度家庭裁判所の許可が必要となり、煩わしさや費用面の負担等により制度活用に躊躇われて、結局のところ『不動産売却をしない』という選択肢を取る親族の方が多いようにも感じます。
その場合高齢者がお亡くなりになられてから売却となり、相続登記代等の費用面の負担や居住用財産の3000万円特別控除が活用出来ないといった税金面の負担が生じます。
職業柄『生きているうちに処分するというのが理想』だと頭では理解できますが、自分自身が年齢を重ねるにつれ、『なかなか難しい問題だな』としみじみと感じます。
尚、成年後見人制度については、本ブログを鵜呑みにすることなく司法書士等の専門家にご確認ください。