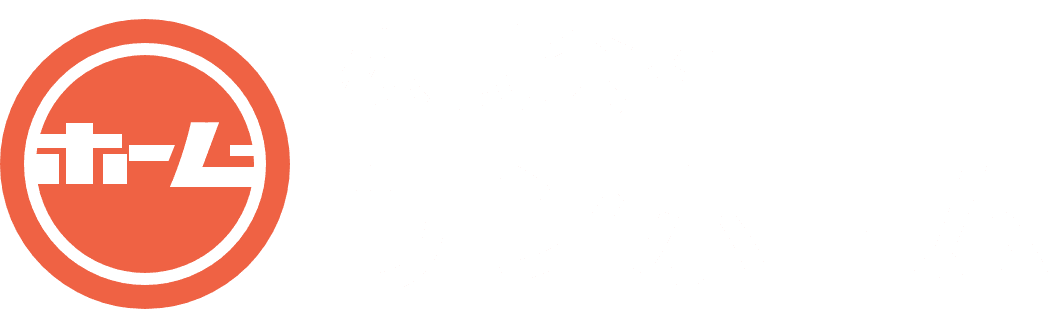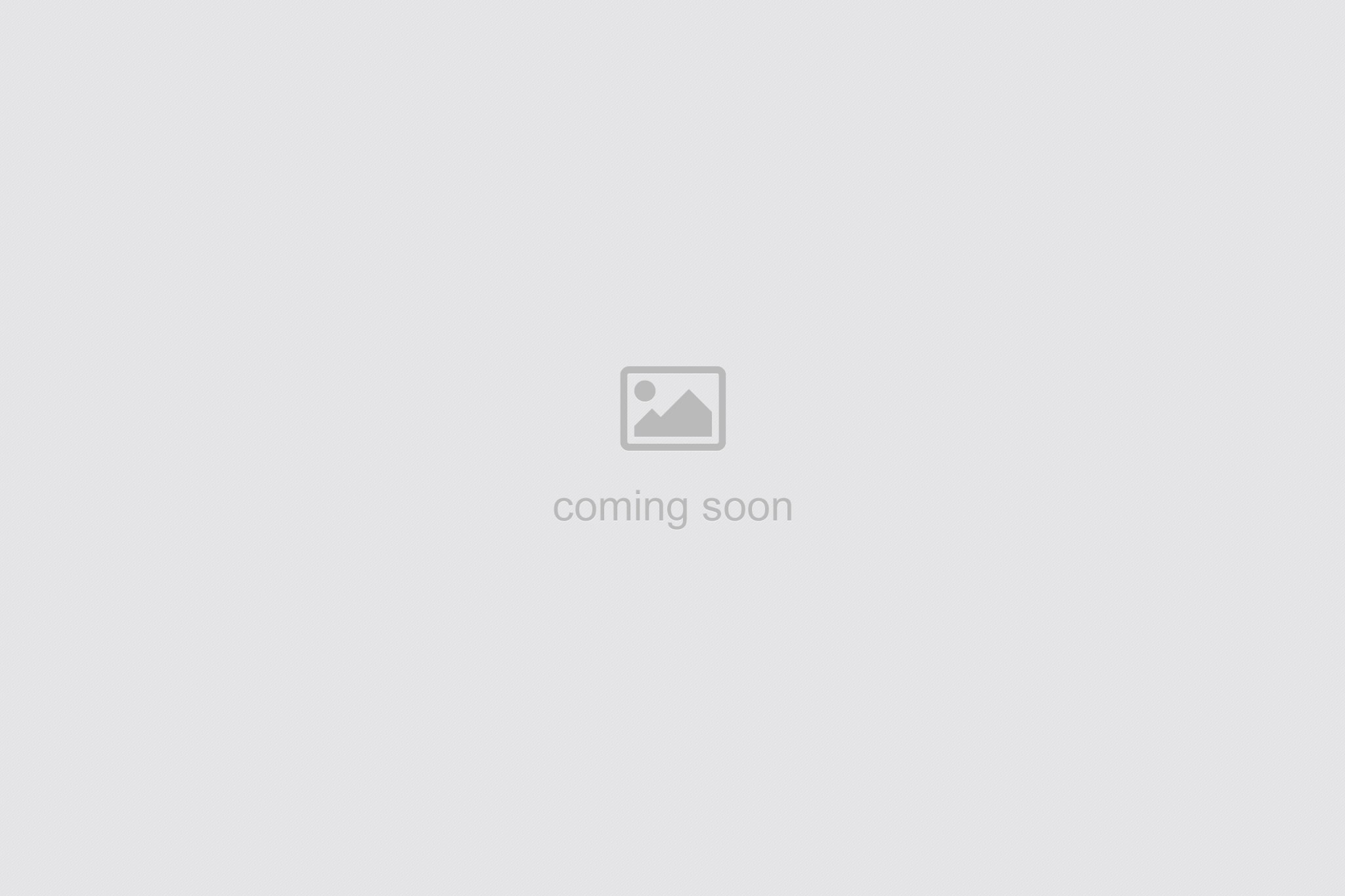ブログ
【親から相続した不動産売却】について(その3)
2022-09-06
カテゴリ:不動産(実家)売却
おはようございます 株式会社 サンホ―ムの清原です。
今回は【親から相続した不動産売却】(その1)・(その2)の続きです。
さらに共有名義にした場合、以下のような揉め事が生じる可能性があります。
3、弁護士を通じて共有物分割請求されることもあります。 共有物分割の種類は次の3つ。
a、不動産を物理的に分ける現物分割
b、共有者の内1人が不動産を取得し、その他の共有者が持分に相当する金銭を取得する代償分割
C、不動産を売却し、売却代金を持分割合で分配する換価分割
各々の詳しい内容については、他に委ねますが、aの方法は、共有不動産が戸建住宅等場合は現実問題として不可能であり、それでも土地のみならば分筆により分けることは可能ですが、分筆後の全ての土地が前面道路(建築基準法上の道路)に面しているか否か、間口が「ある程度」確保されているか否か、向きや方角等、全て同じという訳にはいきません。分筆により土地全体の価値が下がる場合もあります。結局のところ、bやCの金銭面の解決になります。
本ブログテーマからは、少し逸脱してしまいますが、共有物分割請求を受けるということは、投資物件であれば、賃料等の収入が共有者の1人に集中しているか、賃料が適切でないと共有者の1人が判断し『いっそのこと』売却してしまった方が良いと思っているのにも関わらず、他の共有者が応じないという状況が背景があります。
また相続により共有名義にした自宅に関して、以前相談を受けた件について、以下紹介します。
「母親の相続に際し、母親名義であった自宅(兄が母親と同居)を兄弟2人共有名義で相続登記を完了後、数年経過したのち都会に住んでいる弟から弁護士を通じて共有物分割請求(※協議)を受けました。弁護士に相談したところ、『不動産会社に自宅売却依頼したほうが良い』とアドバイスを受けたので、価格査定も含めて売却してほしい。」という内容でした。共有物分割請求のbを検討したが、資金が無いのでCを選択したのかなと理解しましたが、「自分は母親の生前より固定資産税を払い続けている」と納得いかないご様子でした。
(※この件については、自宅が人気スポットでない割に固定資産税評価額が高い点、建物の築年数が古く現況では売却出来ない点(解体せざるを得ない)、そして何より兄弟同士の関係が崩れてしまっていて値段の折り合いがつかないと判断し、丁重にお断りいたしました。)
以上【1~3】に示したように相続不動産については、共有名義にすることなく、例えば「A不動産は兄に、B不動産は弟に」等「1物件1人」に相続登記をすることが、売却を進める上で重要なポイントです。
※尚、共有名義が必ずしもダメというわけではなく、(売主側の)交渉の代表者が明確で、その点につき他の共有者が納得していれば問題はないと思います。
(補足※相談例のように、仮に兄弟との話し合いの中で共有名義にせざる負えない結果になったとしても、弟から持分を買い取るぐらいの資金手当てを、日頃から取組んでいたら良かったのではと思います。なぜなら、弟にとっては1不動産でしかありませんが、兄にとっては大事な自宅なんですから)
※本日はここまで
尚、相続登記・共有物分割請求については、本ブログを鵜呑みにすることなく、必ず司法書士・弁護士等の専門家あるいは法務局に相談してください。