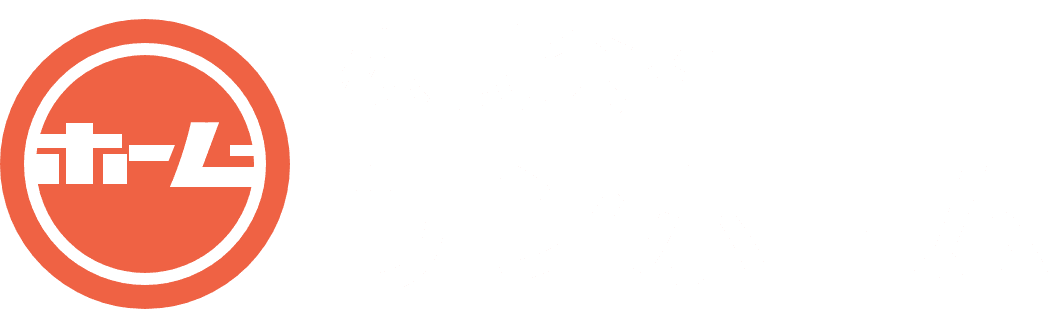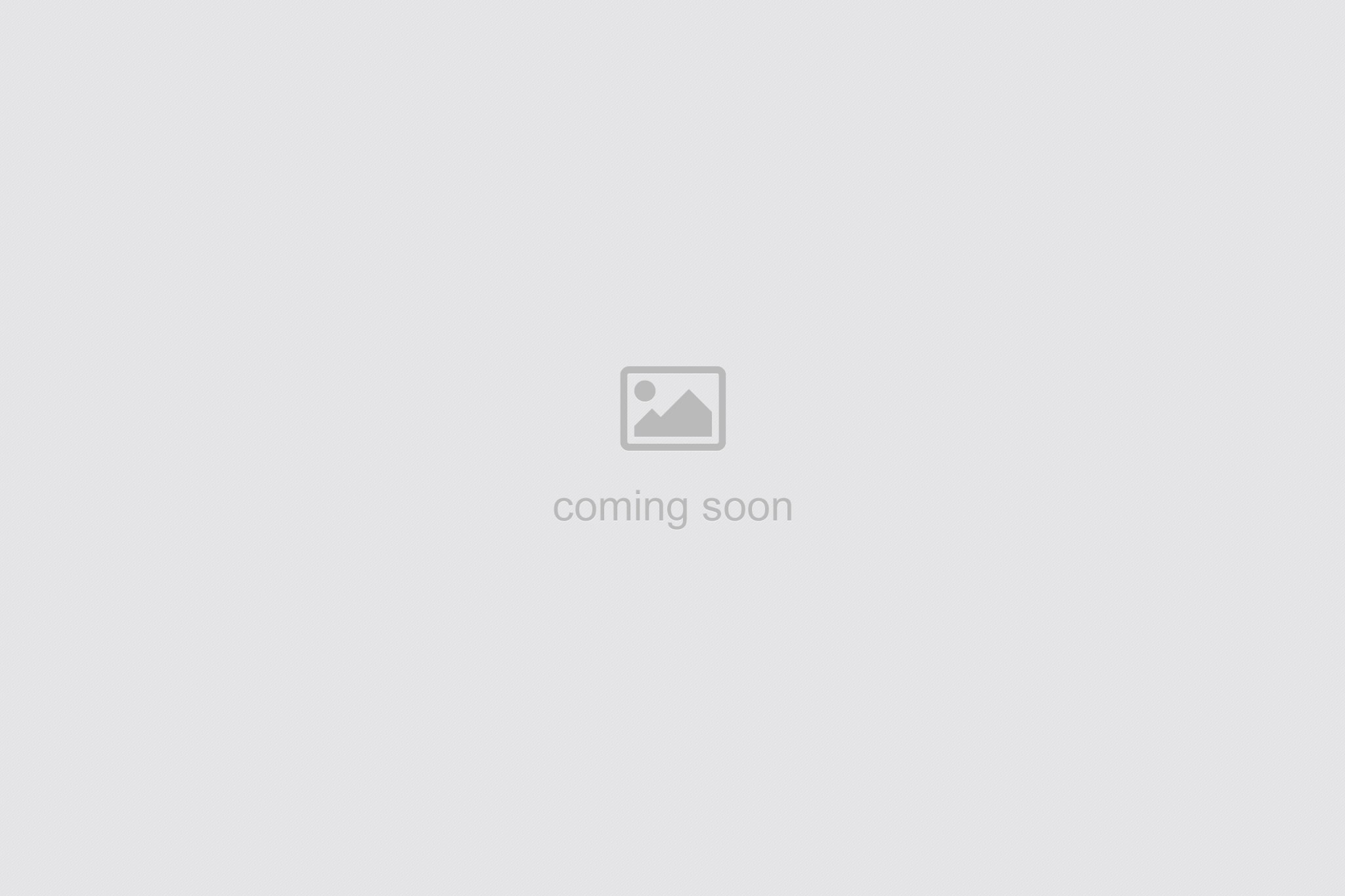ブログ
【親から相続した不動産売却】について(その2)
2022-09-05
カテゴリ:不動産(実家)売却
おはようございます 株式会社 サンホ―ムの清原です。
今回は【親から相続した不動産売却】(その1)の続きの(その2)です。
相続不動産についての注意点について、前回1,2に続いて、以下説明します。
3、相続不動産の内、建物未登記の場合があります。この場合売却するには相続登記ではなく、建物表題登記と保存登記の申請が必要になります。注意点1と同じく、固定資産税納税義務者変更届により建物表題登記・保存登記完了と勘違い。(※このケース、注意点1と同じで割とよくあります。)土地家屋調査士に建物の現況を測って表題登記の申請と司法書士に保存登記の申請を依頼します。土地家屋調査士と司法書士に依頼すれば簡単ですが、法律の知識もない・測量の技術もない素人が行うことは、相続登記以上に難しく基本不可能です。
ですから1~3の注意点がありますから、相続にあたり最低限謄本等を取り寄せて法律上の相続財産の状況を確認することが重要です。
さらに、遺産分割協議書・相続登記はスムーズに完了はしているが、相続財産が共有名義の場合、その共有不動産売却の際以下の注意点というか、相続登記完了時点では想定していなった問題点が浮き彫りになります。
1、共有者全員の意見を、まとめるのが大変。買主との値段交渉の段階で、『その金額は高い』あるいは『安い』とか、『その値段に値下げした根拠は何?』と反対に質問され、結果的に売却まで、かなり時間を要してしまう。不動産の売却はタイミングですので、それでは『売り時』を逃してしまいます。
2、固定資産税の納付につき、市町村役場は必ず共有者の内1人を納税義務者に指定します。従って、固定資産税の納付につき年度毎に共有者で精算すれば話は別ですが、面倒で共有者同志(※共有者は兄弟の場合が大半)請求しづらい。よって、売却時に精算するという暗黙の了解が出来ている場合がほとんどです。相続から1.2年程度なら良いですが、年数が経過するにつれ、結局のところ納税義務者に指定された1人に負担が掛かってきます。よって納税義務指定者は早く処分したい、それ以外の共有者は少しでも高く処分したい等各々の温度差により、1と同じく買主との値段交渉の段階で『売り時』を逃してしまいます。
※本日はここまで
尚、相続登記については、本ブログを鵜呑みにすることなく、必ず司法書士等の専門家あるいは法務局に相談してください。